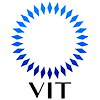自宅兼事務所である「素敬の家」に住み始めてから3ヶ月経ちました。
 家中に温湿度計、環境センサー、電力計などを50個近く設置して、逐一チェックしています。
家中に温湿度計、環境センサー、電力計などを50個近く設置して、逐一チェックしています。
すると、熱や空気がどういうふうに移動しているのか?など、いろんなことが見えてきます。
外気温や天候と連動しており、読み取れることが絶えず変化していきます。
住み始めてからというもの、こんなことを3ヶ月ずっとやっています。
というわけで3ヶ月間の環境レポートをします。
家を建てたいとお考えの方、親族友人で建てたいとお考えの方がいらっしゃる場合は、ぜひご参考になさってください。
■断熱性能について
事務所兼用住宅です。
これでもか! ってぐらい断熱材を組み込みました。
静かで、あったかい家が欲しかったのです。
断熱性能はUA値0.24W/m2・K(断熱等級7 東京ゼロエミ水準3)
気密性能はC値0.1cm2/m2です。
延床面積は約125m2
UA値0.24W/m2・Kという性能が、どのぐらいの性能なのかというと、
家全体の表面積が400m2あったとして、室内20℃・外気0℃の場合、
0.24W/m2・K × 400m2 × 20K = 約2000W
つまり内外で温度差が20℃あった場合、家全体から2000W分の熱が外に逃げ続けるという性能です。
仮に太陽の日射熱、住人や家電からの発熱が合計1500Wあると、500W(こたつ1個程度)の熱源があれば家中を20℃に維持できる、という性能です。
(ここでは換気による熱損失は考慮していません。)
■気密性について
では、気密性能は?
0.1cm2/m2というのは125m2の家があったら12.5cm2の隙間があるということです。
これは家中にある細かな隙間をすべてかき集めると3.5cm角程度の穴しかないということです。つまり名刺より小さい。
※一般的な現代の戸建てのC値は2~5cm2/m2であり、16cm角~25cm角の穴があります。
気密性能が高ければ、一度空気を温めれば、隙間からはほとんど熱が逃げません。
スースーする隙間風も皆無、という状態になります。
、、、こういう家を作ったわけです。
■住心地について
プランニングとか、使い勝手、室内の明るさ、インテリアの質感などは、非常に気に入っています。収納量とか動線とかまったく不満がありません。
だからこれから書く問題点は、あくまで温熱環境、音環境などの話です。
「超・高気密高断熱の家」の住心地、快適性がどうなのかといえば、、、
快適は快適なのですが、想定していた理想と異なる部分も多い。
残念ながら、現段階で100点とはとても言えない。
70点ぐらい?
その後いろいろ対策して85点ぐらいまで来ました。
お金を注ぎ込んでいれば問題なかったはず、と言えることもあるし、
都心ならではの厳しい敷地条件のために、避けられなかった問題も多々あります。
たとえば南側に隣家が迫っていて、冬至の昼間には敷地にほとんど陽が落ちません。
つまり日射熱が足りない。
11月10日 14:00
左側(南側)の家が境界上にせまり、敷地内にはほとんど陽が差さない。
これ以上ないほど、日射条件が悪い。
敷地の日射条件が良ければ、日射熱の活用によって暖房費を0に近づけられますが、都心の場合はある程度仕方がありません。ここが田舎と決定的に違う点で、都心ならではの家造りが必要だと痛感します。
設計上の工夫である程度カバーしましたけど、なかなか100点にはなりません。
この辺は難しいところですね。
少なくとも、冬の朝は外気が0℃であっても、家中どこでも22℃前後を保っています。
■冬の熱源と太陽光パネル、光熱費、蓄電池
ちなみに主たる熱源として動いているのは6畳用エアコン一つです。
夜の0時から7時ぐらいまでは16~17℃設定で、それ以降は19~20℃設定です。
それで家全体が21℃~23℃を保ちます。
(16℃設定というのは寒すぎるのでは?と思われるかもしれませんが、冬の外気を100%エアコンに吸わせているので、実際のエアコンの吹出温度は27℃~35℃ぐらいになり、室温が22℃前後になります。)
また、最近は、夕飯時のリビングで、もう一つのエアコンを補助的に2、3時間程度動かします。22℃の室温を24℃に引き上げるイメージです。
1階のエアコンは24時間つけっぱなしで、エアコンで使う電力は1日あたり8~11kWh(300円前後)です。
太陽光パネルは平均して11kWh/日ぐらい発電しています。
(曇りの日は2~4kWhぐらい、晴れの日は14~16kWhぐらい)
ちなみに、太陽光の売電もありますが、売電量は微々たるもので、住み始めてから32%が自家消費で、全使用量の44%発電しています。
事務所との兼用住宅なので、全体で1日あたり30~35kWh前後使用しており、そのうちパソコン類で5~6kWhぐらい使っています。
(←12月を取り出したもので、自給率40% 自家消費率33%)
ですから7%は売っているということです。
売電額701円、、、。
この7%を使い切るために蓄電池を入れるべきだろうか?
また、一日の消費電力を取り出してみると、
※意外に夕飯時の消費電力が大きい、、、
一般的には太陽光発電は夏に発電量が最大になり、冬は最小となります。
これは太陽高度とパネルの傾斜角度の関係によって変わります。
しかしながら事務所兼用住宅ということもあって、年間を通してどの月も一定量の電力が必要になるので、パネルの設置角度をシミュレートして、毎月平均的に発電できるように設置角度を設定しました。
また、昼間は事務所が稼働しているので、年間を通してほとんど売電がなく、自家消費で使い切ってしまうとの想定から蓄電池は入れませんでした。
■おひさまエコキュート
CHOFUの太陽光パネルで発電し、昼間の発電でお湯を沸かします。
ダイキンの「おひさまエコキュート」です。
370Lのタンクを使っていますが、データを見ると平均的にタンク半分のお湯を毎日使っています。
3人家族の場合、シャワー、洗濯、炊事、洗面で毎日このぐらいは使うということですね。
大体湧きあげるのに毎日4kWh前後使っている計算です。
(80~90℃のお湯を水で薄めて使っているので、370Lと言えども実際は42℃のお湯が740Lあることになります。)

ちなみに我が家は思い切って浴槽を入れませんでした。シャワーだけです。
家族全員が今までシャワーのみで過ごしてきて、ほとんど浴槽に入ることがなかったから、ということもあるのですが、実はもう一つ理由があります。
家の温熱環境が整うと浴槽に入る動機が減っていくと言われています。日本人がお風呂好きなのは、家が寒いことの裏返しでもあり、冷え切った体をしっかりお湯で温めたいわけです。
ならばいっそのこと高断熱化を機に、シャワールームだけで良いか、と決めました。
この辺は各ご家庭の好き好きですが、我が家の場合は、浴室面積を減らして初期費用を抑え、その分、温泉旅行に使うのもいいよね!となったわけです。
■ハイブリッド熱源?
家族もスタッフも全然寒くない、いや、むしろ暑いと言うのですが、私は特に寒がりで、ずっと座って仕事をしていると足元だけが寒くて仕方ない。この3ヶ月で何回か体調を崩しました。どうすれば良いか、運用方法が見えなかったからです。
気流の向き、風速、温度、いろいろ検証しました。
サーキュレータを置く位置を変えたり、エアコンの吹出しの向きを変えたり、、
床面の放射温度は室温より+1、2℃高いと快適、というのはわかっていたので、本当は床下エアコンか床下温水チューブを入れたかったのですが、、、
ちょっと基礎を掘り込むだけで、残土処分費が100万ぐらい簡単に上がってしまうことがわかったので断念したのです。都心は残土処分費も非常に高いです。
とはいえ、仕事中に足元が少し冷たく感じるのはなんとかしないと、、、。
高性能住宅界隈では、「電気生炊きはご法度」という風潮があるのですが、170W程度のパネルヒーターを足元に入れたら、多少改善されました。パネルヒーターを追加で入れようか検討中です。
足元がほどよく暖かければ、室内温度を下げても快適性を得られます。
室温を下げられれば、相対湿度が上がるので、加湿器を過剰に運転せずとも乾燥しにくくなり、快適性を得られます。
床下空間に熱源を入れられない場合は、ハイブリッド熱源を追求するのは、十分にあり得る選択肢だと思います。
すなわちベースとなる温度はエアコンで確保し、足元だけ追加で温めるという方法です。
この辺の運用は試行錯誤中です。
■静粛性
ここが家造りの本丸でした。
私は静粛性を得るために家を建てたかったのです。
断熱や気密性を高めるのは静粛性のためなんです。
ちなみに静粛性というのは「無音」とは異なります。
スタジオの無音室みたいなのとは違うわけです。
体に馴染む静けさといえば良いのでしょうか?
森のような「し・・・ん」とした静かさです。
これを言うと、「適度に音楽とか音があったほうが良い」という方が一定数いらしゃるのですが、これは音楽を聞く、その周りの環境が静かだから快適なのです。
家の前で道路工事していたら、音楽を気持ちよく聞けないでしょう?
さて、高気密高断熱によって、家はとても静かになりました。
外界の音はほとんど気になりません。
夜中になると車の通り過ぎる音がうっすら聞こえますが、通り過ぎれば静けさが戻ります。
、、、ところが、思わぬことがおきました。
家が外音をシャットしたために、内部で発生する音が支配的になったのです。
まず、冷蔵庫がうるさい。
これが一番うるさい。
引っ越しを機に購入したT社の新品です。
室内を漆喰で仕上げたこともあって、コンプレッサー音が反響します。
カーペットがあるにもかかわらずです。
また、12月に入るとさらに異変が起きました。
外気が冷えてきて1台で24時間運転しているエアコンの室外機が猛烈に動き始めたのです。
すると、室外機のコンプレッサーとモーターの低周波音が室内に入ってくるようになりました。
ネットで調べると、こうした家電を起因とした騒音で不眠を抱える人が数多くいることがわかります。特に室外機から発生する低周波音は訴訟が起きるぐらい深刻で、あるゆる建材を伝搬して伝わります。遮音性の高い高気密高断熱住宅であっても、室外からの低周波音は入ってきます。これを断ち切るのは大変難しいようです。
(一般に壁の遮音力は低音域ほど弱い傾向にある。)
(一般に壁の遮音力は低音域ほど弱い傾向にある。)
夜中の2時、4時、5時と断続的に目が覚める日が続き、12月の間は、朦朧とした日々となりました。判断力は鈍るし、何と言っても一日の活力が湧きません。
家はカーペットを多用したので、それなりに吸音するはずでした。
音に関しては、かなり気を配って設計したつもりでした。
それでもこの結果。。。
音は本当に難しいです。
中世ヨーロッパには針だらけの箱に立たせたまま人を閉じ込め、うっかり寝ると針が刺さって寝させない、という拷問があったそうですが、私は自分で設計した家でありながら、針が突き刺さり続けるような1ヶ月を過ごしたことになります。
もう、泣くに泣けない。
なんとかしないと、、、
考えられる限りのことを試しました。
眠りに落ちかけたときに音をキャッチしてしまうと、、、体に鞭打って、無理やり起きて騒音源を特定したり、音を計測する時間が辛かったです。。。
1週間試行錯誤して、ようやく対策と運用方法を見出して、室外機の騒音を鎮めました。
しかし冷蔵庫が最大の難敵でした。
考えられる対策を7種類すべて施しました。
数週間かかりました。
その結果、ようやく気にならないレベルまで落とすことができました。
その日を境に夜中は静まり返り、時折コンプレッサーの音が静かに動きますが、許容範囲となりました。(本当は完全に無音にしたいのですが、流石に無音というわけにはいきません)
|
対策前の冷蔵庫下部の音。 そのために、目が覚めてしまう。 |
対策後で 47Hzで20.7db 全体で32.9db 多少の前後はあるが、冷蔵庫から離れた寝室では以前よりはるかに静か。 |
対策後であっても、コンプレッサーが動くと多少気になる音がする。 45Hz付近と160Hz帯付近が大きい。 |
 |
 |
 |
その結果、寝室は30db前後となりました。
(気になる低周波領域は25dbぐらい)
30dbなんて夜は普通だよ、という人もいるかもしれませんが、エアコンを24時間運転して、安定的な室温を保ちながら静粛性を維持することが難しいのです。
高気密高断熱に加えて、防音・吸音対策もした後の最大の問題は、なんと「電化製品」という結果でした。コンプレッサーとモーター、これは我々に恩恵をもたらす一方で、静粛性を壊す元凶でもあったということです。
一方で、家電メーカーは何をやっとる?、、、とも思うわけです。
冷蔵庫がWiFiにつながります!とか、はっきり言ってどうでもいいだろ!(笑
と、突っ込みたくなるような機能ばかりが謳われています。
家庭用冷蔵庫なんだから、、、工場に設置するわけじゃないんです。
開発リソースを別の方向に向けて、骨太な商品を開発してほしいです。
( と、思うのは私だけ?)
■加湿と結露
加湿器を24時間運転して相対湿度40~50%を維持しています。
湿度が足りなければ喉が痛くなったり、肌がカサカサしたり悩ましいですよね。
冬の外気が1m3あたり2~4gぐらいしかないので、この空気を換気で取り込むと、家はどんどん乾燥していくわけです。
そこで、9Lタンク(4.5Lタンク×2個)を1日2回給水して、10 g/m3前後を保っています。
1日あたり18Lの加湿です。
1日あたり18Lの加湿です。
panasonicの「FE-KXF15」です。
(めんどくさいので、給水自動化を画策しています。
自動化をしやすい設計にしておけばよかったと後悔。。。それにしても大きい、、、じゃま、、、)
一方で、1日に18Lも加湿していれば、結露も気になります。
躯体はぶっちぎりの高断熱にしましたが、
窓は、樹脂製と木製のトリプルガラスのサッシを入れました。
そしてハニカムサーモスクリーンを夜の間、閉じます。
※木製サッシのハニカムは断熱レール仕様です。
↓左側が「防火・APW430」で樹脂サッシトリプルガラス。
右側が「防火・佐藤の窓」で木製サッシトリプルガラス。(ハニカムを下ろした状態)
外気が0℃を下回ってきたら、明け方にほんの僅かですが、樹脂サッシ枠とガラスの下側の接点で結露が生じました。
相対湿度の関係で、表面温度が11℃ぐらいになると結露します。
| 明け方、ハニカムサーモスクリーンを上げた直後。 「防火・APW430」のガラスの結露面を測ると11.2℃ ↓クリックすると結露量と範囲がわかります |
明け方、ハニカムサーモスクリーンを上げた直後。 |
ハニカムサーモスクリーンを降ろさない場合は、 「防火・APW430」は結露していない |
 |
 |
 |
この結露は、窓にハニカムサーモスクリーンをかけるために起こります。
なぜハニカムをかけると結露するのか?
ハニカムサーモスクリーンによって窓の断熱性が劇的に向上するわけですが、この不織布は透湿性があるので、室内の湿気が不織布を超えてガラス側に移動します。
ハニカムには断熱性があるので、室内の熱がサッシ側にいかず、サッシの表面が冷えて結露する、というわけです。
窓ガラスの下側から結露が生じているのは、枠の下端が一番冷えやすいからです。
外付加断熱がある程度厚くなってくると、水切り部材を付ける必要があるため、その部分で断熱欠損が生じます。
スクリーンを降ろさない場合は、今のところ「防火・APW430」も結露していません。
これはガラス表面の温度が室内温度に近づいて、露点になかなか到達しないからです。
—
別日に、試しに加湿器をOFFにして就寝しました。
朝の家の湿度は概ね8g/m3前後
予想通りですが、結露はほぼありませんでした。
、、、が、妻と子供が過乾燥が原因で咳をしていました。
これはいけない!
多少の結露を許容したとしても、適度に加湿をしなければいけないことに気づきました。
結露も僅かなので、さっと拭き取って済ませることにして、様子を見ています。
ちなみに我が家では今のところ、どこにもカビは生えていません。
シャワールームもきれいです。
住み始めて3ヶ月後の浴室
(壁・天井はモールテックス、床は御影石)
これは高気密高断熱、空調・換気計画によって、カビが生える条件を排除しているからです。
このロジックがわからずに家を建ててしまうと事故が起きるかもしれません。
結露や湿気が多いとカビを招きやすくなりますが、これらは物理現象の結果であり、意図的にコントロールできなければ、健康被害を招く可能性もあります。
おまけの話
■2025年の法改正と音問題
2025年4月の法改正によって省エネ義務化となります。
一定の断熱性が確保できない家は建てられなくなります。
おそらく世の中の住宅は高断熱化に流れていくと思います。
そして、建物の性能が上がるにつれて、全国的に音の問題が浮上してくるはずです。
多くの場合、施主様から音のクレームが出ても、「それは家電の話ですから、家の設計とは関係ないです。」と言ってしまうかもしれません。
あるいは空調機や換気装置の音についてクレームが出ても、「音の感じ方には個人差がありますからねえ。」と言って煙に撒いてしまうかもしれません。
間違いとも言えないので、殆どの場合、施主様は何も言えなくなると思います。
でも私は設計者として、それを絶対に言いたくないのです。
私達の生活は電気や家電、空調と切っても切れない関係になってしまったのですから、建築計画はもちろん、騒音の問題についても、再現性のある方法で静かな家を設計したいです。
というわけで、毎日毎日実測して観察して、試行錯誤しています。
家は壮大な実験場になっています。
関連記事
こちらもあわせてお読みください。
東京都の練馬区上石神井に「事務所兼用住宅」を建てました。
緑道沿いの良好な住環境の中、暖かく涼しい住まいになりました。
夜の風景を通して、素材や音、照明の考え方に触れてみます。
外付けブラインドを設置する日射遮蔽の意義を考えるとともに、室内の明るさや雰囲気に及ぼす効果についてみていきます。また、採用する際の注意点についても解説します。
「佐藤の窓」は断熱性能が高い世界最高クラスのサッシですが、生活するうえではブラインドやカーテンも必要です。「佐藤の窓」とハニカムの最適な納まりを実例で示します。